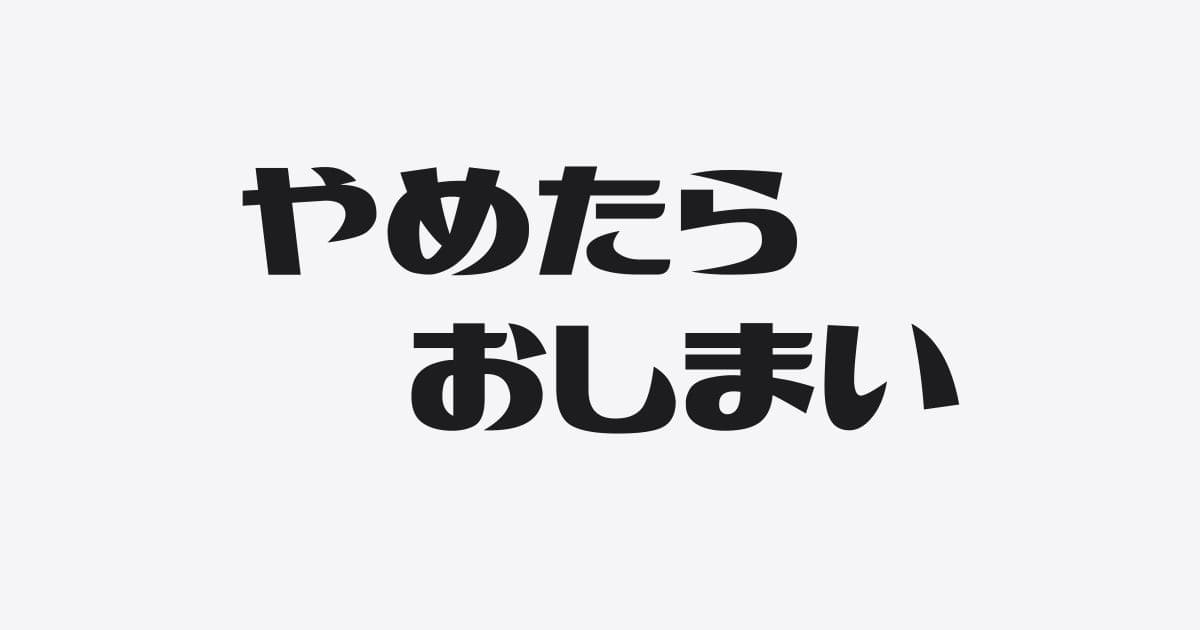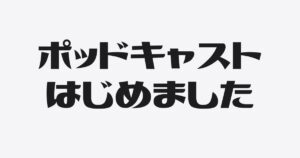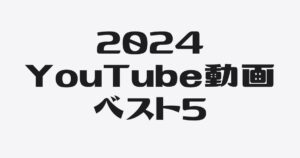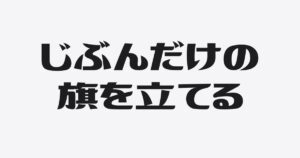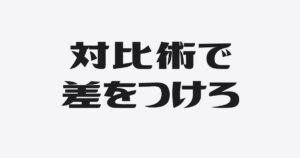発信をなんのために続けるのか、と問われたら。僕は、続けるために続けるのだと答えます。つまり、発信は続けることが目的でいい。その理由を深堀りしてみます。
みなと同じことを言ってもやっても
日々、いろいろと発信を続けています。なかでもこのブログは、もうすぐ9年です。ほかにも、メルマガ、YouTube、音声コンテンツ、各種SNSなど。
その発信について、「なんのために続けるのか?」と問われたら。つまり、発信を続ける目的を問われたら。僕は、「続けるために続ける」と答えます。
いやいや、それでは行為の目的化でしょう?本末転倒でしょう?と、おもわれるかもしれません。発信を続けるには、何を伝えるかが大事なのであり、その前提にあるじぶんの思いこそが大事なのではないか?とも、おもわれるかもしれません。
知ってる。僕も9年のあいだ発信を続けていますから、何を伝えるかが大事なこと、じぶんの思いが大事なことは知っています。みなもそのようなことを言ってますから、知っています。でも、みなと同じことを言っていてもやっていても、みなと同じことにしかなりません。
ここでいう「みな」とは、大勢や多数派という意味であり、みなは発信を続けることができていない。言い換えると、ほとんどすべての人(割合でいえば)が、発信をはじめてはやめてしまいます。でも、やめたらおしまいです。そうなればもう、何を伝えるも、じぶんの思いもありません。
そして僕もまたヒトである以上、あすはわが身です。9年のあいだ発信を続けていますなどといいながら、あすにはやめてしまうかもしれない。だからこそ、発信を続けるために続けるのであり、発信は続けることが目的でいいと考えています。
発信をするなら、もっと「続けること」を重視したほうがいい。それを伝えたくて、セミナーを開催することにもしました。それは後述するとして、まずは、発信は続けることが目的でいい理由について、もう少し深堀りしてみることにします。その理由は3つ、次のとおりです。
- やめたらおしまい
- 継続が成長になる
- 継続が機会になる
このあと、それぞれの理由を解説していきます。
発信は続けることが目的でいい理由
僕が、発信は続けることが目的でいいと考えていることは前述しました。その考えに説得力をもたせるためにも、発信は続けることが目的でいい理由を3つ挙げます。
やめたらおしまい
発信は続けることが目的でいい理由、1つめは「やめたらおしまい」です。これについては冒頭でもいいましたが、大事なことなのでもういちど。
発信は、やめたらおしまいです。あたりまえすぎるほどあたりまえですが、やめてしまえば、何を伝えるかも、何を伝えたいかという思いも、意味を持たなくなってしまいます。
この点では、発信は続けることがすべてだといっても過言ではありません。でも、多くの人は続けられずにやめてしまうのです。僕はじぶんが発信を続けている9年のあいだに、そのようすを見てきましたし、じぶん自身もやめそうになった瞬間はあるのでわかっています。
多くの人は、油断をすれば発信をやめてしまうのです。
でも、発信をやめるのにはそれぞれ「事情」があるのでしょう?と、おもわれるかもしれません。たしかにそのとおりでしょうが、それを言ったらおしまいです。事情という名の言い訳もありますし、じぶんを正当化するために事情をこじつけるのがヒトでもあるからです。
発信をしよう、と決めたときの瞬間を忘れてはいけません。そのときたしかにじぶんは、発信をしようと「決めた」のです。いまのじぶんは、そのときのじぶんに負けていないか。負けていないというのであれば、やめるのもいいでしょう。
ですが、少しでもうしろめたい気持ちがあるのならそれは負けであり、やめる事情など逃げ口上に過ぎません。僕の価値観では、たとえ他人に負けても、けしてじぶんに負けるなです。
とはいえ、発信を続けるのもラクではなく、発信を続けるためのコツや方法は僕なりにあります。そのあたりは、今後のセミナーでお話しする予定です。
継続が成長になる
発信は続けることが目的でいい理由、2つめは「継続が成長になる」です。僕がわざわざいわずとも、周知の事実でしょう。継続はチカラなりの言葉もあります。
僕がこれまで発信を続けることで、少なからず、発信のスキルを高めることができました。ブログであれば、当初は構成も文章もいまと比べるとヒドいものです。それと比べれば、以前よりは「伝わる文章」を書けるようになったといえます。
文章を書くスピード(思考するスピード、タイピングするスピードなど)も上がりましたし、同じ時間で発信できる量が増えたのも、スキルが高まったといえるでしょう。
さらにいえば、発信に対するハードル(抵抗感)もだいぶ下がりました。ブログのように文章を書くのはもちろん、YouTubeをはじめたことで、カメラの前でひとりで話すことに違和感はなくなり、音声コンテンツをはじめたことで、やはり、マイクに向かってひとりで話すことに違和感はなくなりました。
音声コンテンツについては、基本、ピンマイク片手に散歩をしながら収録しているので、「どこでだって発信はできるのだ」という感覚を強められたのも、ひとつの成長だと考えています。
なにごともコツコツ続けていればチカラはつくわけで、発信もチカラがつけば、「また次の発信を、また別の発信を」という意欲もわくものです。結果として、僕は発信の量・種類を増やすことができたのだと理解しています。
誤解を恐れずにいえば、続けていればおのずと成長するということです。続けることを目的にするだけでも成長できるということです。やめるとは、その成長を放棄することでありもったいなくはないですか?やめる前には自問してみるのをおすすめします。
継続が機会になる
発信は続けることが目的でいい理由、3つめは「継続が機会になる」です。続けていればいつか良いこともある、みたいなハナシがありますが。まさに、発信を続けていることでえられる機会もありました。
最たるものを挙げるなら出版です。つい先日は、2冊めの単著が出版となりました。
『税理士必携 銀行融資を引き出す仕訳90』
(リンク先はAmazonの商品ページです)
この前段には、共著での出版があり、1冊めの単著があり。きっかけは、ブログを続けていたことでした。もちろん、ブログを続けていたからといって、必ずしも出版できたとは限りません。ですが、ブログを続けていなければ「出版の機会はなかった」と言い切れます。
ブログに限らず、発信に限らずですが、継続の先には機会があるものです。ここでいう機会とはつまり、チャンスを指しています。続けている限り、いつもワンチャンある(やめればチャンスはゼロ)。そういう思いでいることも、発信を続ける動機にはなるでしょう。
また、チャンスとは別の意味での機会もあります。僕は、ブログを続けているなかで、「税理士としての銀行融資支援」という軸を見つけることができました。
それまでは、税金や経理といった税理士にありがちなネタしかなかったところ、ブログを続けているうちにネタ切れを起こし、それをきっかけにして「税金や経理とは別の軸を見つけなきゃ」という考えを持てたのですね。
おかげでブログだけではなく、銀行融資支援の依頼を受けられるようになったり、銀行融資支援に関する出版もできるようになりました。やはり、ブログをやめていたら実現しなかったことだろうとおもっています。なので、いずれ機会になると信じて続けるのもよいのではないでしょうか。
まとめ
発信をなんのために続けるのか、と問われたら。僕は、続けるために続けるのだと答えます。つまり、発信は続けることが目的でいい。その理由を深堀りしてみました。
- やめたらおしまい
- 継続が成長になる
- 継続が機会になる
これらが説得力となり、少しでも多くの人が発信を続けることにつながればと考えています。これに関連して、以下の内容を今後のセミナーでお話しする予定です。
- 発信を続けるモチベーションのつくり方
- 発信を続けるためにはどうするか?の方法
- 発信量を増やすにはどうするか?の方法
- そもそも発信の量と質をどう考えるか?
- 発信の種類とそれぞれの効果とは?
- 商業出版できるようにと僕がやってきたこと
- 重版されるようにと僕がやってきたこと
- 出版・重版によって僕が得られたこと など
その他、セミナーの詳細やお申し込みは以下のリンクからご確認ください。
ちなみに、上記セミナーは出版を含む内容ですが、出版を目指さない方であっても、発信をするのであればお役立ていただける内容かとおもいます。