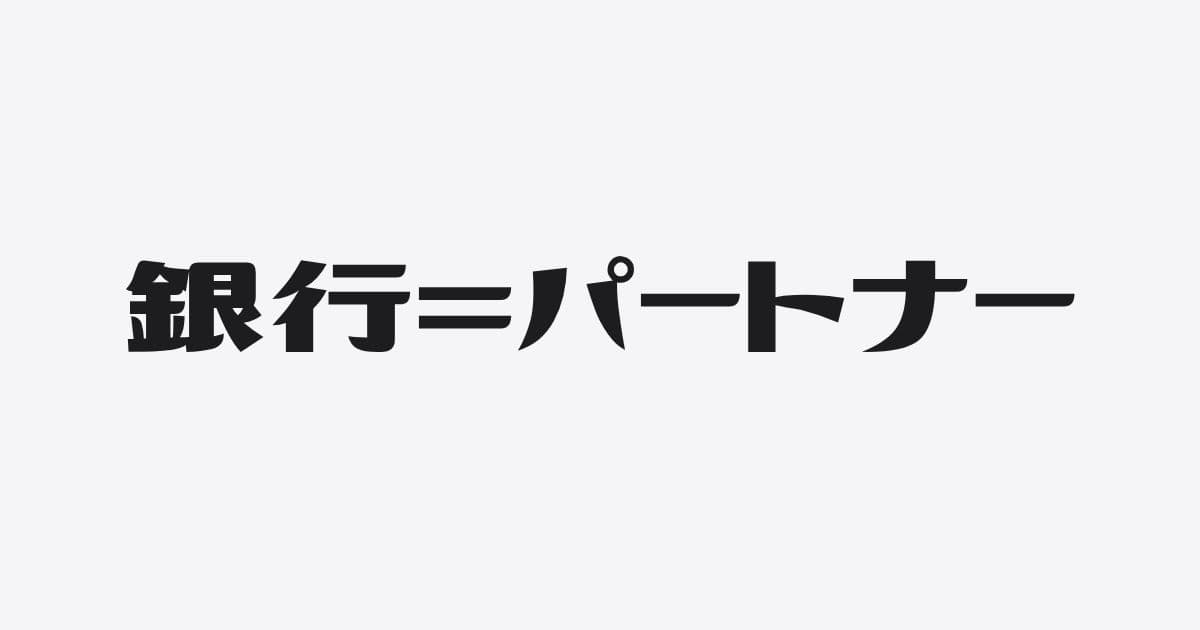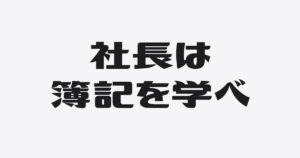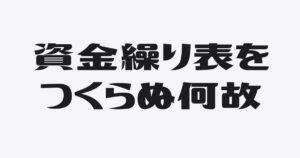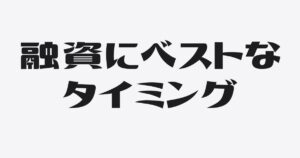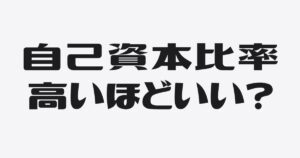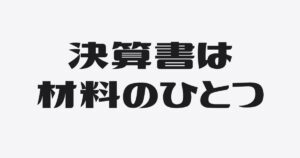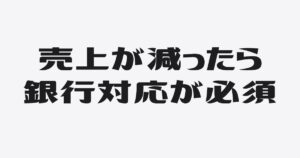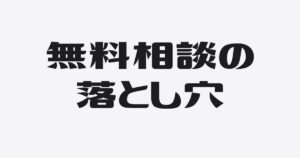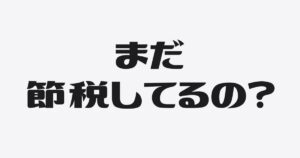金融庁は銀行に「本業支援」を求めていますが、自社の取引銀行はそのように動いていますか?決算書の話しかしない銀行では物足りないかも。社長が「真のパートナー」を見極めるための3つのサインと、これからの銀行との付き合い方を解説します。
決算書の話だけで、事業の「未来」を語れない銀行で満足ですか?
銀行融資の相談に行っても、担当者の話題が「決算書の数字」や「担保・保証」ばかりで、社長の事業の強みや将来の戦略について深く聞いてこない…そんな経験はありませんか?
金融庁はいま、銀行に対して「決算書や担保に依存せず、事業の内容や将来性を評価する(=事業性評価)」ことや、融資以外の「本業支援(ビジネスマッチングや経営改善アドバイスなど)」を強く求めています。
これは、社長にとって銀行を「単なる資金の貸し手」から「事業の未来を共に考える真の経営パートナー」へと関係性を深める絶好のチャンスです。
しかし、現実にはその変化に対応できず、従来の姿勢から抜け出せない銀行も少なくありません。会社の成長を本気で考えるなら、社長も「どの銀行と、より深く付き合うべきか」を選ぶ目を持つべきでしょう。
資金支援だけでなく、会社の未来を一緒に考えてくれない銀行は、パートナーとして少し物足りないかもしれません。
「本業支援」への本気度を見極める3つのサイン
銀行の「本気度」は、日々の対応に表れます。社長が「真のパートナー」を見極めるためにチェックすべき3つのサインを見ていきましょう。
サイン1:決算書や数字の話「しか」しない
銀行担当者が訪問してきても、話題が「今期の業績はどうですか」「試算表をください」だけで終わっていませんか?
たしかに財務データ(定量評価)は重要です。しかし、銀行が本当に「事業性評価」をしようとしているなら、決算書には表れない「非財務情報(定性評価)」にも関心を持つはずです 。銀行は融資先を順位付けしたうえで、各融資先に対する「融資姿勢」を決めるために格付をしていますが、その格付は決算書だけで決まるわけではありません 。
「社長がいま、経営課題として感じていることは?」「他社と違う強み(差別化ポイント)は?」「業界の動向をどう見ていますか?」といった、事業の中身に踏み込む質問がない場合、その銀行はまだ「事業」ではなく「数字」しか見ていない可能性が高いです。
サイン2:融資以外の「提案」が一切ない
銀行の役割は、融資(資金支援)だけではありません。金融庁も銀行に対し、そのネットワークや情報を活かした「本業支援」を求めています 。
たとえば、販路拡大に繋がりそうな「ビジネスマッチング(取引先の紹介)」、活用できそうな「補助金・助成金の新着情報」、「経営改善に役立つアドバイス」など、融資以外の提案がメインバンクからまったくない場合、その銀行は「本業支援」への意欲が低いと言わざるを得ません。
良いパートナーであれば、社長が抱える課題(たとえばローカルベンチマークで共有した課題)に対して、融資以外の解決策も一緒に考えてくれるものです 。
サイン3:「金融仲介機能のベンチマーク」などに後ろ向き
これは少し専門的ですが、金融庁は銀行に対し、「金融仲介機能のベンチマーク」という指標(事業性評価への取組状況など)の「自主的な」開示を促しています。義務ではないからこそ、ここに銀行の本気度が表れます。
社長から「御行の本業支援への取り組み(ベンチマークなど)はどうなっていますか?」と尋ねたときに、明確な資料を示せなかったり、説明が曖昧だったりする場合、その銀行(あるいはその支店・担当者)の意識は低い可能性があります。
本気で取り組んでいる銀行は、「経営者保証に依存しない融資の割合」や「経営改善支援先数」といった自らの取り組みを、ディスクロージャー誌などで積極的にアピールしようとするはずです。
これからは社長が「銀行を育てる・選ぶ」時代
金利が上昇し、コロナ融資後の倒産も増える(代位弁済はコロナ以前より高い水準で急増しています)これからの時代、銀行との関係はこれまで以上に重要になります。
もしいまの取引銀行が、決算書の話ばかりで事業の未来に無関心なら、まずは社長から積極的に情報開示(経営計画書やロカベンの提示など)を行い、対話を求めてみましょう。ここでは、銀行員を「育てる」意識も大切です。
それでも銀行の姿勢が変わらないのであれば、それは社長がメインバンクとの関係性を見直す(たとえば、サブバンクとの取引を厚くする)きっかけかもしれません。
銀行に「評価される」のを待つだけでなく、社長自身が「事業を理解し、本気で伴走してくれる銀行」はどこかを見極め、主体的に関係を築いていく。その姿勢こそが、これからの銀行再編時代を乗り切るカギとなります。