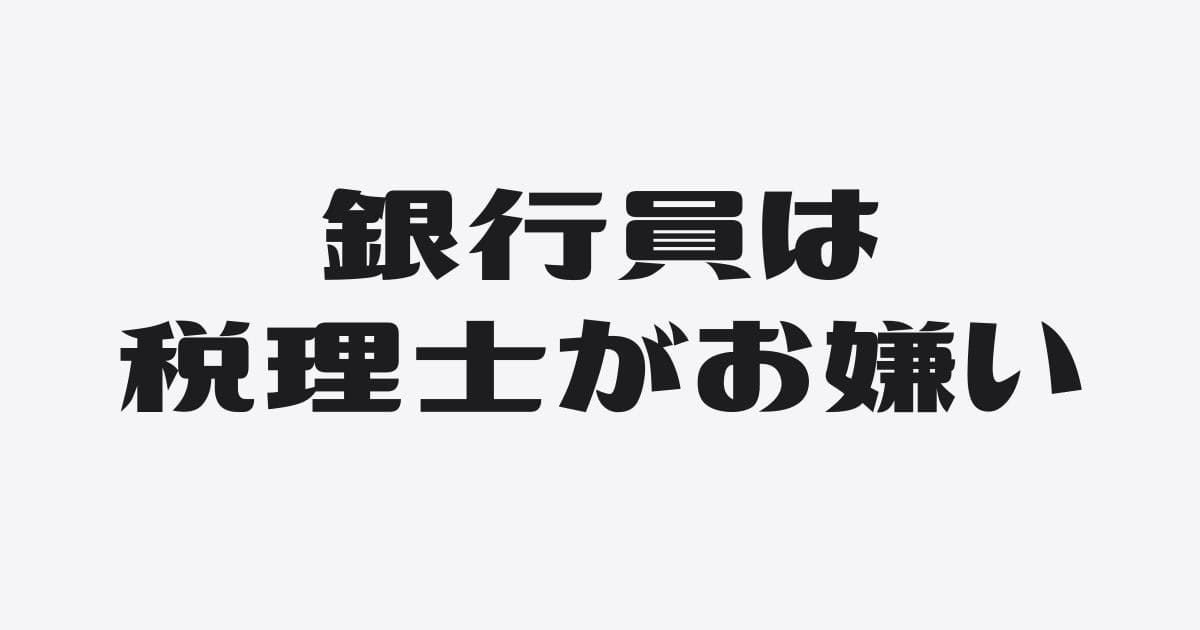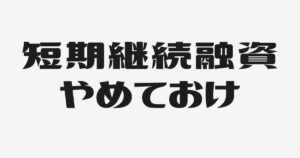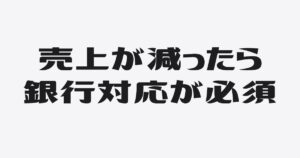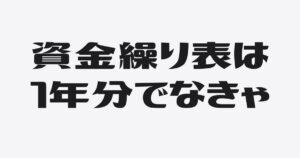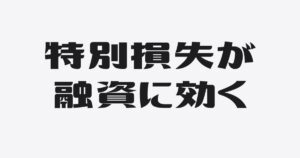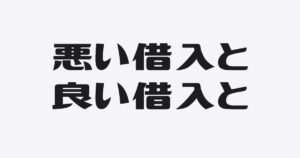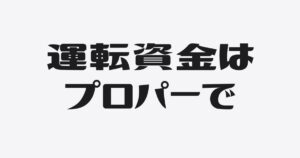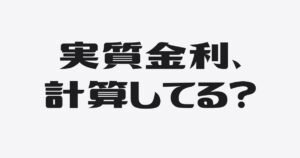「元銀行員の融資コンサルタントのなかには、税理士を嫌っている人がいる」という話があります。ではなぜ、税理士が嫌われるのか。その理由を理解して、銀行融資に役立てましょう。
元銀行員融資コンサルタントは税理士が嫌い
先日、会話のなかで次のようなことをいわれました。
「元銀行員の融資コンサルタントのなかには、税理士を嫌っている人がいますよね?」
ちなみに、僕は税理士です。そのうえで銀行融資の支援をしています。そんな僕自身もまた正直なところ、前述の「いわれたこと」を感じるタイミングはあります。
さらには、元銀行員の方から実際に「税理士が嫌い」といった話をうかがったこともありました。なので、「元銀行員の融資コンサルタントのなかには、税理士を嫌っている人がいる」というのも気のせいではないようです。
ではなぜ、税理士が嫌われるのか?その理由を、元銀行員の方からうかがったこともふまえてまとめると次の3つです。
- 財務を知らない
- 銀行を知らない
- 借入を知らない
これらの理由を理解することは、税理士がお客さまの銀行融資に関わるうえで役に立ちます。税理士ではなく社長であっても、同様に役に立つはずです。
というわけなので、「元銀行員の融資コンサルタントに嫌われないようにしよう」とか、「元銀行員の融資コンサルタントに物申す」といった意図はないことを念のため申し添えます。
元銀行員融資コンサルタントに嫌われる理由
「元銀行員の融資コンサルタントのなかには、税理士を嫌っている人がいる」という話について、税理士が嫌われる理由は3つです。それぞれの理由を解説します。
財務を知らない
元銀行員融資コンサルタントに税理士が嫌われる理由、1つめは「財務を知らない」です。財務とは、誤解を恐れずにひとことでいえば「将来の資金繰り」です。
その財務に対して、税理士の専門分野である「税務」があります。これまた誤解を恐れずにいえば(否、恐れているからこその枕言葉…)、「過去の後始末」です。
決算書にもとづき、会社が納める税金を計算する。決算書は「過去の情報」であり、だとすれば税金の計算は過去の後始末だといえます。いまさらどうこうできない、ということです。
もちろん、税金も大事なことではありますが、過去のみにとらわれていれば、将来への備えが疎かになってしまいます。結果、将来の資金繰りがおざなりになると、最悪、会社は倒産です。
では税理士が財務を理解しているか、お客さまの資金繰りにまで関わっているかといえば、必ずしもそうではありません。僕が知る限り、「資金繰り表のつくりかたがわからない」という税理士もいます(ディスりではありません。わからないならわかるように学べばよいだけです)。
加えて、節税の名のもとに利益を減らす(銀行は融資しづらくなる)、おカネがあるなら繰上げ返済をする(銀行からすると迷惑だし、以降の融資はしづらくなる)といったことを、お客さまに提案する税理士もいるようです(そう聞きます)。いずれも資金繰りには悪影響であり、財務の面でデメリットがあるといえます。
すると、「この税理士は、財務のことをわかっているのか?(わかっていない)」となるわけです。これが嫌われる理由になりえます。もっとも、税務や会計をわかっていない銀行員(元を含む)もいるため、そういう意味では「おあいこ」です。
よって、元銀行員融資コンサルタントも税理士のどちらも、「マウントをとる(財務を知らない!とか、税務を知らない!とか)」のは何か違うといってよいでしょう。
銀行を知らない
元銀行員融資コンサルタントに税理士が嫌われる理由、2つめは「銀行を知らない」です。元銀行員の税理士でない限り、「銀行のことを知らないくせに(知ったふうなことをいうな)」といったハナシになります。
僕はといえば、元銀行員ではありません。なので銀行のことは知りませんが、お客さまの銀行融資の支援をしています。もう少し正確にいえば、「各銀行内部のことは知りませんが、銀行の基本的な考え方は知っているので、銀行融資の支援ができている」ということになるでしょう。
ひとくちに銀行(信用金庫・信用組合なども含め)といってもいろいろです。支店ごとにも違いがあります。時間がたてば変わりもします。だとすれば、銀行内部のことも千差万別であり、ひとりの銀行員(元も含む)が知りうるものでもありません。
だから僕は、個々の銀行事情を事細かに知る必要はないと考えていますし、代わりに、多くの銀行に共通するであろう「基本的な考え方」をきちんと理解していれば十分だとの考えです。
この点、基本的な考え方を知らない、わかっていない税理士はいますから気をつけなければいけません。もともとは僕自身がそうでしたから、本当にそうおもいます。つまり、税理士はお客さまのためにも基本的な考え方は理解していたほうがよいし、社長自身もまた理解していたほうがよいです。
なお、基本的な考え方とはたとえば、決算書から見た借入の難易度があります。決算書の見方というのは、銀行によって全然違うということはありません。銀行であれば、おおむねいっしょです。ゆえに汎用性があるし、だからこそ基本的な考え方を理解することが役立ちます。
借入を知らない
元銀行員融資コンサルタントに税理士が嫌われる理由、3つめは「借入を知らない」です。これは前述の「銀行を知らない」の続きにあたります。銀行からすれば、融資をわかっていないということであり、融資はそんなに甘くないとの思いです。
さきほど、基本的な考え方が大切だといいました。ところが、そのようなことをいえば、銀行員(元を含む)の方からは「そんなにカンタンな話ではない」とか、「そんなに銀行は甘くない」といった反論にあうこともあります。「借入(融資)を知らない」として嫌われます。
いっぽうで、僕自身は「できるだけカンタンにしたい」との考えです。言い換えると、融資が難しいケースでの、複雑な話はしたくないし、必要ないとも考えています。なぜなら、融資の難易度が低いうちであれば、複雑な話は必要ないからです。
もう少し具体的にいうと、利益が出ているうち・預金が多いうちであれば融資の難易度は低く、銀行からもスムーズに借りられるということです。ところが、赤字になっておカネもないとなってからでは融資の難易度も上がり、銀行も警戒します。すると、複雑な銀行対応も必要になってしまうでしょう。
だから、そうはならないように、カンタンな話で済むように、基本的な考え方を理解して確実に実践することを僕はおすすめしています。基本的な考え方については、1冊の本にまとめました。よろしければ、参考にしていただければとおもいます。
『税理士必携 顧問先の銀行融資支援スキル 実装ハンドブック』
(リンク先はAmazonの商品ページです)
本のタイトルには「税理士必携」とありますが、税理士ではなく社長であっても、お読みいただける内容です。
まとめ
「元銀行員の融資コンサルタントのなかには、税理士を嫌っている人がいる」という話があります。ではなぜ、税理士が嫌われるのか。その理由を理解して、銀行融資支援に役立てましょう。
- 財務を知らない
- 銀行を知らない
- 借入を知らない
これらの理由を理解することは、税理士がお客さまの銀行融資に関わるうえで役に立ちます。税理士ではなく社長であっても、同様に役に立つはずです。