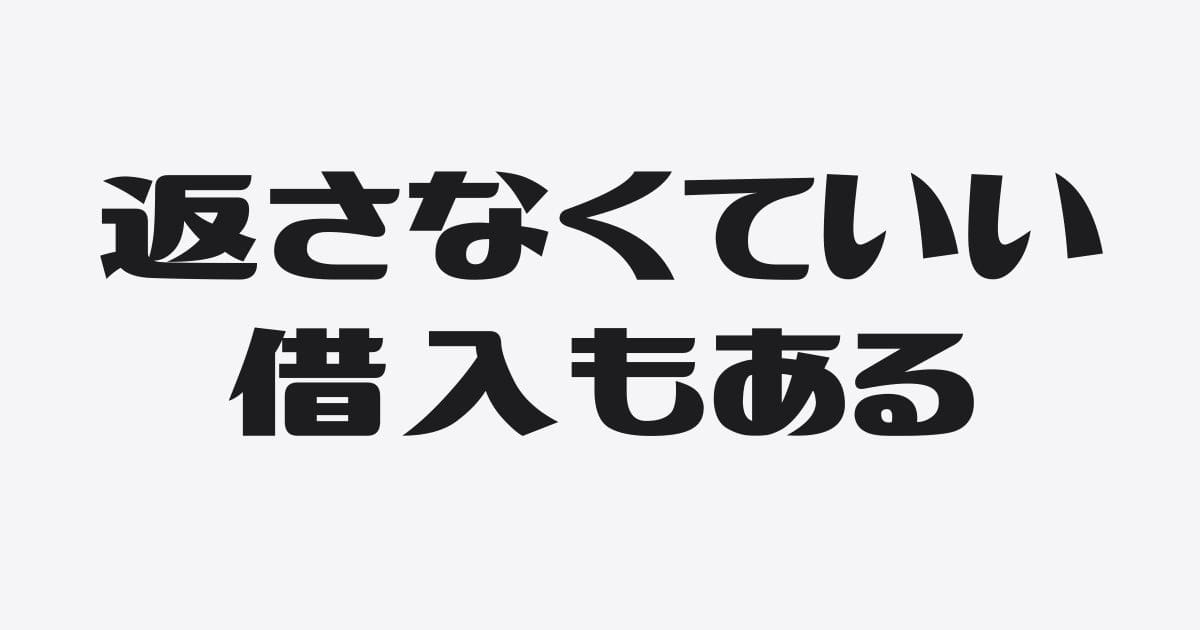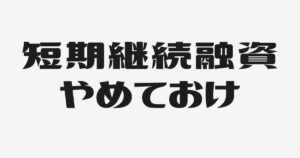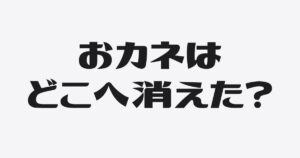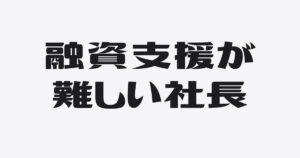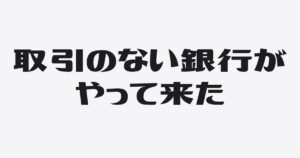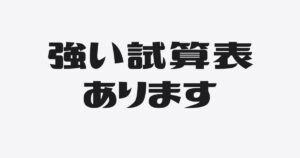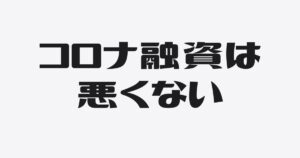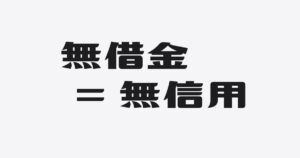銀行から運転資金として借りたおカネを、毎月コツコツ返済している。でも、実はそれ、間違った対応かもしれません。本記事では、運転資金の借入を返済してはいけない理由について解説します。
「借入は返済するのがあたりまえ」の罠
銀行から融資を受けたら、きちんと返済計画を立てて、毎月コツコツと返していく。これは、社長にとって「あたりまえ」のことでしょう。たしかに、その姿勢は誠実であり、基本的には正しいものです。
しかし、もしその借入が「運転資金」であるならば、話は別です。実は、本来、運転資金の借入は(事業を継続している限り)返済する必要がない、と言ったら驚かれるでしょうか?
もちろん、これは暴論でもなければ、借金を踏み倒せと言っているわけでもありません。銀行融資と会社の財務を考えるうえでの、きわめて合理的で、重要なセオリーなのです。
にもかかわらず、多くの中小企業の社長が、このセオリーを知らないばかりに、運転資金の借入を毎月分割で返済し、自社の資金繰りを不必要に悪くしてしまっている現実があります。
そこで本記事は、なぜ運転資金の借入は返済してはいけないのか、その理由と、本来あるべき借り方について解説していきます。この記事のポイントは以下のとおりです。
- そもそも運転資金とは何か
- 運転資金の返済原資は何か
- 短期継続融資で借りるべき
運転資金の借入を返済してはいけない3つのポイント
「借金なのに返さなくていい」という、一見すると不思議な話。これを理解するためには、まず「運転資金」そのものの正体を知る必要があります。3つのポイントに沿って、順番に見ていきましょう。
ポイント1:そもそも運転資金とは何か
運転資金とは、会社が日々の事業を回していくために必要なおカネのことです。なかでも、特に重要なのが「経常運転資金」であり、簡単な算式であらわせます。次のとおりです。
- 経常運転資金 = 売掛金 + 棚卸資産 ー 買掛金
この算式が示しているのは、商品を仕入れてから(買掛金の支払い)、それが売れて(棚卸資産)、最終的に代金が入金される(売掛金の回収)までのあいだに、事業活動の中で「寝てしまうおカネ」です。
会社が事業を続ける限り、この「寝てしまうおカネ」は常に一定額、発生し続けます。したがって、経常運転資金が多い会社ほど、資金繰りは厳しくなるのです。
ここで、工場の機械などを買うための「設備資金」と比べてみましょう。設備資金の借入は、その機械が利益を生み出し、減価償却されていくのと同じ期間で返済していくのが合理的とされています。つまり、「おわり(完済)がある借入」です。
いっぽうで、経常運転資金は、会社がいまの事業規模を維持する限り、永続的に必要なおカネであり、「おわりがないおカネ」と言えます。というように、理論上は返済する必要がないにもかかわらず、現実には多くの会社が「運転資金」として借りたおカネを、毎月分割で返済しています。
これは、会社の資金繰りに、重たい足かせをはめているようなものだと理解しましょう。
ポイント2:運転資金の返済原資は何か
では、理論上、運転資金の借入を返済するためのおカネ(返済原資)は、どこから生まれるのでしょうか?
それは、経常運転資金の算式のなかにあった「売掛金」と「棚卸資産」をすべて現金化することで生まれます。具体的には、すべての得意先に売掛金を支払ってもらい、すべての在庫を売り切っておカネに変える、ということです。
では、すべての売掛金を回収し、すべての在庫を売り切るのは、いったいどんなときでしょうか? それは、自社が事業をやめるときです。言い換えると、事業を継続している限り、運転資金の借入を完済するための返済原資は、本来、会社のなかには生まれない、ということになります。
だから、事業を続ける限りは「借り続ける」のが理屈です。この考え方は、銀行が本来、運転資金はプロパー融資で貸し出すべき理由でもあります。売掛金や棚卸資産が、銀行にとって実質的な担保のような役割を果たしている、と言えるからです。
何の疑いもなく、銀行に言われるがまま信用保証付き融資を受け入れることがないようにしましょう。経常運転資金は、本来、プロパー融資で借りるべきなのです。
ポイント3:短期継続融資で借りるべき
ならば、返済する必要がない運転資金を、どのように借りるのよいのか?
答えは、「短期継続融資(別名:短コロ)」です。具体的には、「手形貸付」や「当座貸越」といった形式で、期間1年などの短期で融資を受けます。そして、1年後の期日が来たら、銀行があらためて審査のうえで問題がなければ、期日を更新(書き換え)する。これを繰り返していくのです。
この方法であれば、毎月の元金返済はなく、支払うのは利息だけ。会社の資金繰りは、分割返済に比べて格段にラクになります。にもかかわらず、なぜ多くの中小企業が運転資金を分割返済しているのでしょうか。
理由としては、銀行側の都合(管理のしやすさなど)や、会社の信用力がまだ低く、銀行がリスクを取れないといった事情があります。また、社長自身がこの理屈(運転資金は短期継続融資で借りるべき)を知らず、銀行から提案されるままに分割返済の契約をしてしまっているケースも少なくありません。
よって、社長がこの理屈を理解して、「運転資金なので、短期継続融資でお願いできませんか?」と交渉することは重要です。それが認められれば、会社の資金繰りは大きく改善する可能性があります。
まとめ
「借入はすべて返済すべき」という考えは、必ずしも正しくありません。なぜなら…
- 経常運転資金は、事業を続ける限り永続的に必要なおカネである
- その返済原資は事業をやめる時にしか生まれないから
- ゆえに本来の借り方は、毎月の元金返済がない「短期継続融資」
多くの中小企業の社長が、この理屈を知らないために、不必要な返済負担で資金繰りを悪化させています。
まずは、自社の借入が「設備資金」なのか「運転資金」なのかを区別すること。そして、もし運転資金を分割返済しているのであれば、銀行に「短期継続融資」への切り替えを相談してみる。
この知識を持って、実際に行動を起こすことこそが、資金繰り改善の一歩になります。