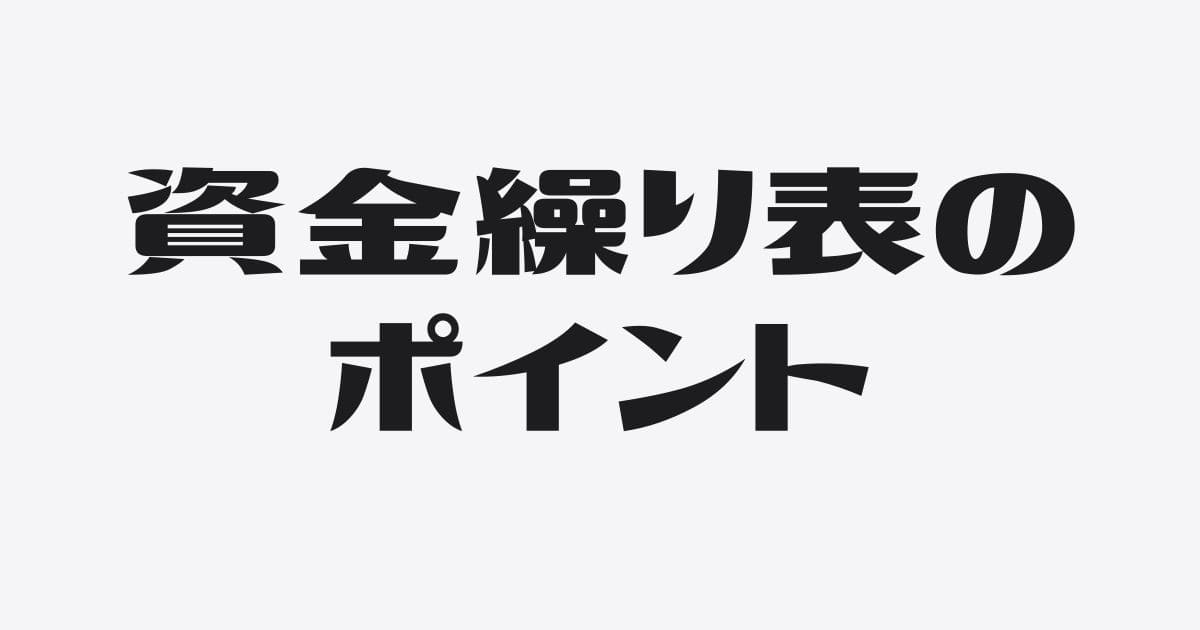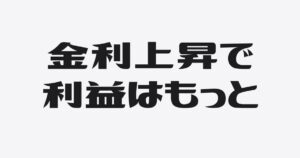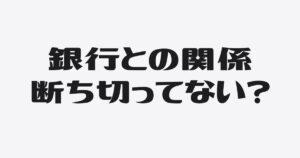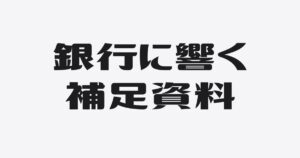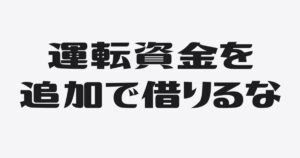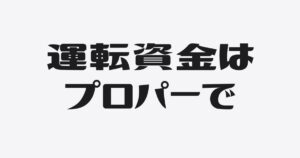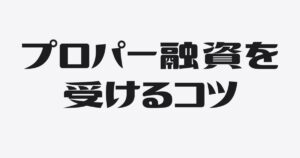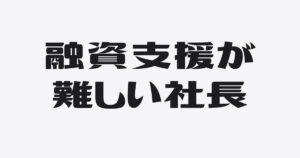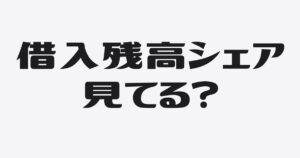銀行に提出する資金繰り表の確認ポイントをお伝えします。そのポイントを押さえていないと、せっかく資金繰り表を提出しても逆効果…ということにもなりかねません。
貸したおカネをきちんと返してもらえるか
銀行から融資を受けるのであれば、銀行に資金繰り表を提出することをおすすめします。提出を求められなかったとしてもです。
理由はいうまでもありません。銀行にとっては、貸したおカネをきちんと返してもらえるかが関心事なのであり、それを確認するためには資金繰り表が欠かせないからです。
なお、ここでいう資金繰り表とは、向こう1年ていどについて「各月の入金・出金・預金残高」の推移をまとめた帳票をいいます。これにより、毎月末にどれだけのおカネがあるのかを見通せるわけです。いっぽうで、決算書や試算表からでは見通すことができません。だから、資金繰り表が欠かせないのです。
以上をふまえて、銀行に提出する資金繰り表の確認ポイントをまとめます。ぜんぶで3つです。
- 複数のシナリオ
- 月末残高の増加
- 借入計画の加味
これらのポイントを押さえていないと、せっかく資金繰り表を提出しても逆効果…ということにもなりかねないので気をつけましょう。このあと、各ポイントを順番に解説していきます。
銀行に提出する資金繰り表の確認ポイント
銀行にとっては、貸したおカネをきちんと返してもらえるかが関心事であることは前述しました。だとすれば、「借りたおカネをきちんと返せるのか」を示すことが大切だとわかります。そのポイントになるものが以下の3つです。
複数のシナリオ
銀行に提出する資金繰り表の確認ポイント、1つめは「複数のシナリオ」です。
資金繰り表をつくるには、損益予測が必要です。損益とはつまり、売上や費用の予測(計画)にもとづく利益の予測であり、その損益予測にもとづき資金(預金)の動きを考えます。
とはいえ、損益の予測などできるものでもない。とくに売上はお客しだいだし、予測なんてできない。という「現場の声」はめずらしくありません。だから資金繰り表はつくりにくいし、つくっても意味がない、とクチにする社長もいます。
ですが、資金繰り表は「占い」ではありません。予測があたったからいい、あたらないからダメというものではありません。将来を予測し、必要に応じて備える、行動を早めるところに価値があります。逆に、資金繰り表がないと場当たり的になり、対応は遅れがちです。
そこで、予測が難しいのであれば、複数のシナリオで資金繰り表をつくってみましょう。おすすめは、楽観シナリオと悲観シナリオ、その中間シナリオの3つをつくることです。
楽観シナリオとは、伸ばせる可能性として上限の売上を前提とするシナリオをいいます。これに対して悲観シナリオは、落ち込む可能性として下限の売上を前提とするシナリオです。そのうえで、中間シナリオは楽観シナリオと悲観シナリオの中間の売上を前提とし、いわば成り行き(現状維持)のシナリオになります。
銀行に提出する資金繰り表というと、楽観シナリオのようなものだけをつくりがちですが、あわせて中間・悲観シナリオも用意することで、予測の説得力が高まります。上だけではなく、下も見ていることがわかるからです。また、悲観シナリオがあることで、より早く備えることもできます。
月末残高の増加
銀行に提出する資金繰り表の確認ポイント、2つめは「月末残高の増加」です。
再三の繰り返しですが、銀行にとっては、貸したおカネをきちんと返してもらえるかが関心事になります。にもかかわらず、資金繰り表を見たときに、毎月末の預金残高が減っていくようであればどうでしょう?当然、心配になります。
したがって、銀行に資金繰り表を提出するのであれば、毎月末の預金残高は増えていくものでなければいけません。少なくとも、資金繰り表のはじめの預金残高を維持すること。最終月末の預金残高が、はじめの預金残高よりも減少しているようではいけません。
複数のシナリオをつくりましょう、といいました。楽観シナリオであれば、預金残高は増加していくことが多いはずです。ところが悲観シナリオともなれば、放っておけば預金残高は減少してくことになるでしょう。
だとすれば、原価率を下げる、固定費を減らす、固定資産を売却する、保険を解約する、社長個人から借入するなども検討して、預金の減少を食い止めることになります。それを、資金繰り表に織り込みましょう。
実際には、月末の預金残高が減少していく資金繰り表を、銀行に提出している会社はあるものです。銀行の立場で考えれば、それがいかに心配な資金繰り表であるかはわかるでしょう。
逆に、預金が減るような前提(≒悲観シナリオ)であっても、資金繰り表から早めの備えが読み取れれば、銀行は「計画性の高さ」や「管理能力の高さ」を感じるものです。結果として、柔軟な対応を期待できるようになります。資金繰り表の月末残高の減少を放置してはいけません。
借入計画の加味
銀行に提出する資金繰り表の確認ポイント、3つめは「借入計画の加味」です。
月末残高の増加について前述しました。この点、「銀行からの借入も含めて」でかまいません。つまり、銀行から借入できれば預金は増えますから、借入計画を資金繰り表に織り込むことで月末残高が増加しているのであればOKです。
ただし、当然ながら現実的な借入金額である必要はあります。その具体的な目安がいくらなのかという話は別の機会に譲るとして、借入をすれば返済がツキモノです。よって、資金繰り表には借入の金額と返済の金額とを織り込まなければいけません。
たとえば、900万円の運転資金を借りて5年返済を予定するのであれば、毎月15万円の返済を資金繰り表の支出として記載します。そのうえで、資金繰りがきちんとまわるのかが銀行の関心事です。
返済とあわせて、利息の支払いも織り込みます。実際には金利はわかりませんから、そこも予測です。よくわからないのであれば、ひとまずは3%くらいで計算しておくとよいでしょう。要は、利息の支払いも資金繰りに織り込まれていることが大事なのであり、多少ズレることに問題はありません。
そうして借入計画を資金繰り表に織り込むことで、銀行は融資の検討がしやすくなります。どれだけの融資額が必要なのか、融資をした場合には返済してもらえるかの判断材料になるからです。逆に、そういった資金繰り表がないと銀行は検討がしづらく、会社は融資が受けにくくなります。
まとめ
銀行から融資を受けるのであれば、銀行に資金繰り表を提出することをおすすめします。そこで、銀行に提出する資金繰り表の確認ポイントをお伝えしました。
- 複数のシナリオ
- 月末残高の増加
- 借入計画の加味
これらのポイントを押さえていないと、せっかく資金繰り表を提出しても逆効果…ということにもなりかねないので気をつけましょう。実際のところ、ポイントを押さえていない資金繰り表が散見されます。結果として、融資を受けにくくしている可能性があります。